病院のチーム医療を主導する
- 広告用アカウント any creative
- 2025年1月2日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年3月6日
特集
生命をささえる薬剤師
―薬剤師ならではの専門性を発揮して、褥瘡治療の質を高める―
帝京大学ちば総合医療センター 飯塚雄次さん 鈴木里恵さん
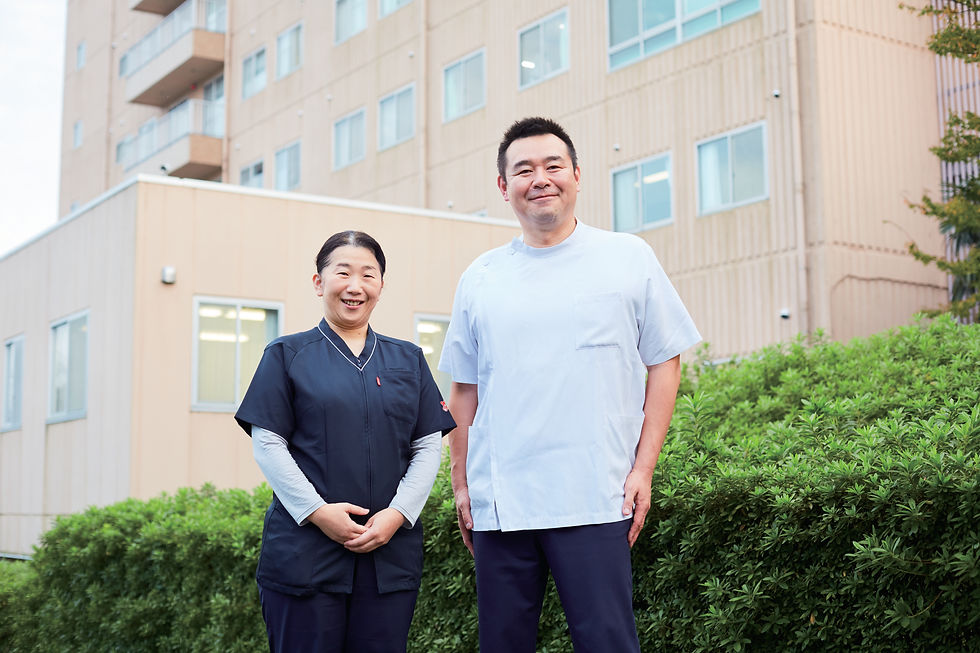
医療が高度に進歩する今、治療を担うのは医師だけではありません。医療現場では、複数の医療職がチームを組み、それぞれの持つ高い専門性を発揮しながら、一人の患者の治療にあたる「チーム医療」がスタンダードとなっています。千葉県市原市にある帝京大学ちば総合医療センターの「褥瘡対策チーム」で活躍する、薬剤師の飯塚雄次さんと、看護師の鈴木里恵さんに、チームでの仕事内容や、薬剤師が治療に参画することの効果などを伺いました。
褥瘡対策チームの一員として薬物治療の責任を持つ

飯塚雄次さん(以下飯塚):帝京大学ちば総合医療センターには、チーム医療を提供する専門チームとして、感染対策チーム、緩和ケアチームなどがありますが、その中のひとつに「褥瘡対策チーム」があり、皮膚科の医師、「皮膚・排泄ケア認定看護師」の資格を持った看護師、理学療法士、薬剤師などで構成されています。今日、一緒にお話をする鈴木さんは、看護師として参加しています。
褥瘡とは、寝たきりなどで身体の位置や向きを変えられなくなると同じ場所に長時間体重がかかり、血流が悪くなって皮膚や皮下組織が壊死した状態のことです。一般には「床とこずれ」とも呼ばれています。骨が見えるくらいに傷が深くなってしてしまうこともあり、傷口からの細菌感染を防ぐためにも、患者さんの状態を見極めて適切な治療方法を選択することが重要です。
鈴木里恵さん(以下鈴木):看護師は、褥瘡ができた患者に薬剤の塗布、患部を保護する基※剤を使った処置をしますが、褥瘡ができる前の予防をすることも大きな仕事です。全ての患者に対して、身体の状態を確かめ、予防・治療いずれであっても、状態に合った寝具やオムツの選定も行います。
飯塚:薬剤師は、薬に関わることには全て責任を持ち、医師には最新の薬剤の情報を伝え、看護師には効果的な塗布の方法や使用時の注意事項などを伝えています。
薬を使って治療効果を上げるためには、患者の情報を正確に理解していなければいけません。鈴木さんをはじめ、看護師からは患者の栄養状態や動ける範囲、患部の状態など、的確な情報をいただけて、またもちろん処置やケアもしっかり行っていただけるので、安心して薬の使用ができます。本当に頼りにしています。
チーム医療では、各専門職が何ができるのか、理解し合うことがとても大切です。看護師の皆さんは、自分の仕事をしっかりするだけでなく、薬剤師や他の専門職の仕事の範囲や特徴も理解してくれるので、スムーズな褥瘡治療に貢献できています。
鈴木:チーム内の情報共有では、各専門職がその後何をするのか、看護師側からは何を頼むのか、そうしたことをよく考えて、情報を選別して提供してより有効な治療につなげることを心がけています。
また、退院した患者で、家庭でケアを続けてよくなった、という人に外来で会うことがあります。退院後にもしっかりケアができて、再発していないという患者は増加していて、このチームが、退院後のケアを含めて、わかりやすいアドバイスをできている成果だと感じています。
薬剤師ならではの科学的視点が治療効果を上げる
飯塚:褥瘡対策チームの薬剤師だけでなく、チームに属さない薬剤師にも、可能な限り、褥瘡回診に同行するように言っています。若い薬剤師を見ていると、褥瘡という疾患に興味を持つ人は多くないのですが、本来は薬剤師は皆、褥瘡の知識を持っているべきだと考えています。
鈴木:薬剤部の皆さんの参加はもちろん、飯塚さんは、実習の薬学生にも治療の見学を勧めてくれて、若い世代の意識が変わっていくのではないかと感じています。
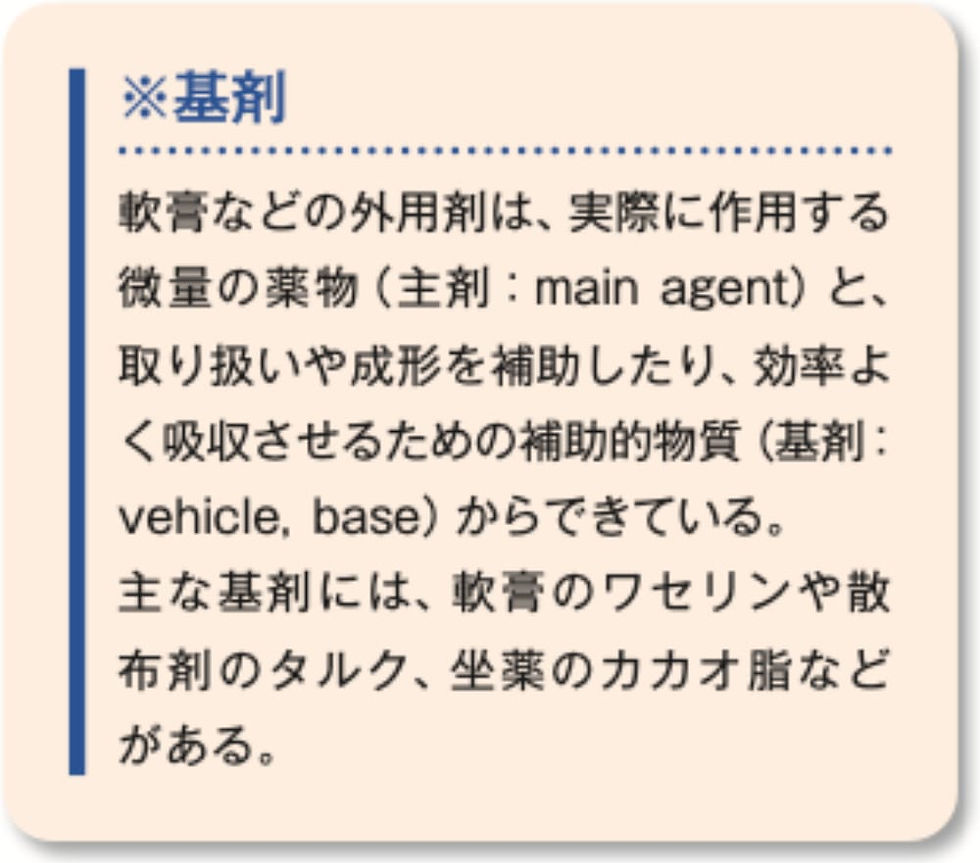
皮膚・排泄ケア認定看護師として専門の勉強をして、薬剤についてはある程度の知識を持っていますが、飯塚さんからは、薬剤のベースとなる基剤のことなども教えてもらって、幅広い知識を身につけることができました。薬剤師ならではの視点があるから、治療の質が上がっています。
飯塚:皆さんも、べたっとした軟膏や、さらっとしたクリームなど、塗り薬の違いを体験したことがあるのではないでしょうか。それは、薬効成分ではなく基剤の違いで、創傷の治療では、基剤の使い分けで治療効果が変わってきます。褥瘡では特に、基剤の選択が重要です。たとえば、褥瘡が治っていくためには、適切な湿潤環境に保つ必要がありますから、傷から出てくる浸出液が多すぎる場合は吸収性の高い基剤を、乾燥してきたら水分を保持したり足したりする基剤を選びます。

薬剤師は、大学で製剤学を学び、実際に軟膏やクリームをつくる実習をしてきています。皮膚科や形成外科の医師は、もちろん診療の中でそうした剤形選びのスキルは積んでいますが、基剤について専門教育の中で学ぶのは薬剤師です。こうした科学の視点から、薬効以外の部分も含めて薬をみることができますし、その視点を持って治療に参加することで、褥瘡治療の効果を上げることができるのです。
鈴木:基剤も含めて、薬は進歩しているので、最新の情報を共有できる点も助かっています。医師も「飯塚さんが言っていた薬を使ってみたい」と言うことがあり、飯塚さんからの発信があって、この病院の褥瘡治療のスタンダードが決まっていくような側面もあります。
飯塚さんは地域のネットワークづくりにも熱心で、市中の薬局の薬剤師との連携もとってくれています。退院後も病院で行った治療を続けられるのは、退院後に利用する薬局に患者情報を伝えて協働できる薬剤師の力も大きいと思います。
勉強会を立ち上げ地域全体の褥瘡治療の質を上げる
飯塚:褥瘡は、患者本人が痛みがあって苦しいことはもちろん、傷が深い時は見た目によるショックも大きく、家族が自責の念を抱えてしまうこともあります。生活の質への影響も大きく、メインの疾患の治療の妨げになる可能性もあり得ます。とても重要な疾患なのです。
在宅医療も増える中、地域全体で褥瘡に対する意識を高め、治療の質を上げる必要があります。そこで、6年ほど前に、市原市、茂原市、長生村の3自治体の医療職を集めた勉強会「褥瘡ゼロの会」を立ち上げました。多職種が集まり、お互いの専門知識・技術を学び会う機会にしています。
鈴木:飯塚さんがこの病院に来る前から、この勉強会で知り合っていましたので、飯塚さんがこちらに来てくれると聞いた時には、「頼りになる人がくる!」と、心強く思いました。
動画配信やe-ラーニングを活用して「褥瘡ゼロの会」を発展させていく方法を一緒に考えて、一人でも仲間を増やしていきたいですね。
飯塚:地域の薬局薬剤師に向けて、褥瘡回診に同行できる研修も開催しています。また、褥瘡治療やケアについて、勉強会を開きたいといわれれば、どこにでも出向いていきます。病院内の治療や予防の質を上げることはもちろん、地域全体の活動にも、より力を入れていきたいと考えています。






